「あれ?前にも言いましたよね?」
言われてないのに、まるで何度も伝えたかのように指摘してくる上司。
心当たりのない言葉に、あなたは戸惑い、冷や汗をかくことはありませんか。
まるで記憶喪失になったかのような不安、もしかしたら自分が間違っているのかという自己嫌悪感。
しかし、その恐怖の根源はあなたの記憶力ではなく、もしかしたら上司の言動そのものにあるのかもしれません。
この記事では、そんな「言われてないのに前にも言ったよね」上司に悩むあなたへ。
具体的な体験談を交えながらその驚くべき心理を深掘りし、明日から使える効果的な対処法を徹底解説します。
「前にも言ったよね」上司の具体的な言動と恐怖体験

「前にも言ったよね」という上司の言葉は、状況によって部下に様々な恐怖感を与えることがあります。
以下に具体的な言動と、それによって生じる恐怖体験について解説します。
曖昧な指示後の指摘
上司が口頭で曖昧な指示を出しただけで具体的な資料や確認の機会を与えないまま後日
「前にも言ったよね?」と指摘してくるケースです。
部下が指示の意図を正確に理解できていなかったり、指示の全体像を把握できていなかったりする場合に起こりやすいです。
指示された内容が不明確だったため、部下はどのように業務を進めて良いか分からず、不安な気持ちで作業に取り掛かります。
後日上司から「前にも言ったよね?」と指摘された際、言われた覚えのない内容に混乱し、自分の記憶力に自信を失います。
「また何か重要なことを見落としてしまったのではないか」
「上司は私に不信感を抱いているのではないか」
といった恐怖感に襲われ、萎縮してしまいます。
曖昧な指示のせいで何度も同じような指摘を受けるのではないかという予期不安も生じ、上司とのコミュニケーションが億劫になります。
記憶違いの押し付け
上司が過去の指示や会話の内容を誤って記憶しているにも関わらずそれを部下に
「前にも言ったよね?」と一方的に押し付けてくるケースです。
客観的な証拠がない場合や部下が反論しにくい立場であることを利用して行われることがあります。
明らかに言われていないことを「言った」と断定されることで部下は強い不当感を覚えます。
「なぜ私の記憶が否定されるのか」「上司は自分の間違いを認めないのか」といった不信感が募ります。
自分の認識が間違っているのではないかと疑心暗鬼になり、上司の言葉を鵜呑みにせざるを得ない状況に恐怖を感じます。
上司の機嫌を損ねることを恐れ事実と異なることを認めてしまうことで今後の業務にも支障が出るのではないかという不安も抱えます。
高圧的な態度
「前にも言ったよね?」という言葉を見下すような態度や威圧的な口調で言ってくるケースです。
部下に対して精神的な圧力をかけ、反論させないようにする意図が見られます。
高圧的な態度で「前にも言ったよね?」と言われると部下は強い威圧感を感じ恐怖を覚えます。
「何か反論したら、さらに強く責められるのではないか」
「上司の機嫌を損ねて今後の評価に影響するのではないか」
といった不安が頭をよぎり何も言い返せなくなってしまいます。
上司の顔色を常に窺いながら仕事をするようになり、精神的なストレスが蓄積していきます。
自由な意見や質問をすることが困難になり職場での孤立感や無力感を覚えることもあります。
質問を封じる言動
部下が指示内容について質問しようとした際に
「前にも言ったよね?」と遮ったり「自分で考えろ」と突き放したりするケースです。
部下の理解不足を認めず、質問すること自体を否定するような態度が見られます。
指示内容に疑問や不明点があっても「前にも言ったよね?」と言われることで部下は質問することを躊躇するようになります。
「また同じことを聞いたら怒られるのではないか」
「質問すること自体が自分の能力不足を露呈するのではないか」
といった恐怖感から、十分に理解できないまま業務を進めざるを得なくなります。
その結果ミスが発生したり業務効率が低下したりする可能性がありさらに上司からの叱責を招くという悪循環に陥ることがあります。
公開の場での指摘
チームミーティングや他の社員がいる前で、部下に対して
「前にも言ったよね?」と指摘するケースです。
部下に恥をかかせたり、見せしめにしたりする意図が感じられます。
大勢の前で「前にも言ったよね?」と指摘されると部下は強い羞恥心や屈辱感を覚えます。
「周りの人は自分のことをどう思っているだろうか」
「上司はなぜわざわざ皆の前で私を貶めるのか」
といった不安や不信感が募ります。
職場で孤立するのではないかという恐怖や、今後の人間関係への悪影響も懸念されます。
上司への不満や怒りが募る一方で、立場上何も言い返せないという無力感に苛まれます。
責任転嫁
業務のミスや問題が発生した際に、実際には指示を出していなかったり曖昧な指示しかしていなかったりするにも関わらず
「前にも言ったよね?」と部下に責任を押し付けるケースです。
自分の責任を認めず、部下に責任を転嫁する上司の言動に、部下は強い憤りを感じます。
「なぜ私が責任を取らなければならないのか」
「上司は自分の保身しか考えていないのか」といった不信感が募ります。
そんな状況が続くと次第に上司への信頼感を完全に失い今後の協力関係を築くことが困難になります。
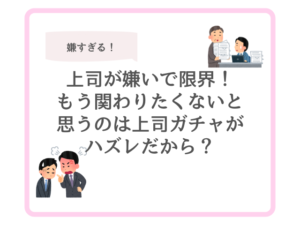
なぜ?「前にも言ったよね」と言ってくる上司の心理を考察

「前にも言ったよね」と言われていないことを指摘してくる上司の心理は一つではなく様々な要因が複雑に絡み合っている可能性があります。
以下に、主な心理的な考察をいくつか挙げます。
- 指導力の欠如と責任転嫁
- 記憶の歪みと認識の齟齬
- パワーハラスメントと支配欲
- コミュニケーション不足と確認不足
- 高い期待と焦り
- 単なる口癖やコミュニケーションの悪癖
指導力の欠如と責任転嫁
自分の指導が不十分であったり指示が曖昧だったりした自覚があるにも関わらずそれを認めずに部下の理解力不足や記憶力不足に責任を転嫁しようとする心理が考えられます。
「前にも言ったよね」という言葉で、自身の指導責任を回避し、部下にミスや遅延の責任を負わせようとするのです。
これは、自己保身の表れであり、自身の評価を下げたくないという心理が働いている可能性があります。
記憶の歪みと認識の齟齬
上司自身が過去の指示や会話の内容を曖昧に記憶していたり誤った認識をしていたりする可能性があります。
しかし、自分の記憶違いを認めることに抵抗があるため、「前にも言った」という言葉を無意識に使ってしまうことがあります。
特に多くの部下を抱えている場合や複数のプロジェクトを同時進行している場合など記憶が曖昧になりやすい状況下ではこの心理が働きやすくなります。
パワーハラスメントと支配欲
意図的に「前にも言ったよね」という言葉を使うことで部下を混乱させたり不安にさせたりしようとするパワーハラスメントの意図が隠されている可能性も否定できません。
部下を精神的に追い詰め、優位な立場を確立しようとする支配欲の表れと言えるでしょう。
このような上司は、部下の自信を失わせ、自分のコントロール下に置こうとする傾向があります。
コミュニケーション不足と確認不足
上司が一方的に話しただけで、部下の理解度を確認するプロセスを怠っている場合があります。
「言ったつもり」になっているだけで実際には十分に伝わっていなかったり部下が理解する時間を与えられていなかったりするのです。
この場合「前にも言ったよね」という言葉は自身のコミュニケーション不足を棚に上げ、部下の確認不足を責める意味合いを持ちます。
高い期待と焦り
部下に対して高い期待を持っているが故に一度伝えたことは当然理解しているはずだという思い込みが働いている場合があります。
また業務の進捗に対する焦りから「何度も同じことを言わせるな」という苛立ちが「前にも言ったよね」という言葉に表れることもあります。
単なる口癖やコミュニケーションの悪癖
深い意図はなく、単に「前にも言ったよね」という言葉が口癖になっている可能性も考えられます。
特に忙しい状況下や複数の人に指示を出す際に確認を怠り反射的にこの言葉を使ってしまうことがあります。
しかし意図がない場合でも、部下にとっては不快な言葉であることに変わりはありません。
「前にも言ったよね」上司への効果的なコミュニケーション術
「前にも言ったよね」という上司への効果的なコミュニケーション術は誤解を防ぎ自身の身を守るための重要なスキルです。
指示や確認事項は必ずメモを取り、復唱する
上司からの指示や確認事項を受けた際はその場で必ずメモを取る習慣をつけましょう。
重要なポイント、期日、担当者などを具体的に記録します。
そして、メモを取り終えたら、「念のため確認させてください。
〇〇の件で、△△を□□までに、担当は私でよろしいでしょうか?」
といった形で、復唱を行い、上司の認識と自分の理解に齟齬がないかを確認します。
この行動は上司に対して注意深く話を聞いている姿勢を示すとともに言った言わないの論争を未然に防ぐ効果があります。
もし、上司が「前にも言ったよね」と指摘してきた場合でも
「はい、〇月〇日にこのようにメモを取らせていただきましたが認識に誤りがありましたでしょうか?」
と冷静に確認を促すことができます。
口頭だけでなく、メールやチャットなどで記録を残す習慣をつける
口頭でのやり取りは、どうしても記憶違いや認識のずれが生じやすいものです。
重要な指示や決定事項については、口頭での確認に加えて、必ずメールや社内チャットなどの文書で記録を残すように心がけましょう。
「先ほどお話いただいた〇〇の件、念のためメールにて内容を送らせていただきました。ご確認いただけますでしょうか?」
といった形で、上司に確認を促すことも有効です。
文書で記録を残すことで、後日「前にも言ったよね」と指摘された際「〇月〇日のメールでご確認いただいた内容と認識しておりましたが相違がありましたでしょうか?」
と客観的な証拠に基づいて反論することができます。
疑問点はすぐに質問し認識の齟齬を防ぐ
指示内容や確認事項について少しでも疑問や不明な点があればすぐに質問するようにしましょう。
「恐れ入りますが、〇〇の部分について、もう少し詳しくご説明いただけますでしょうか?」や「念のため確認させてください。〇〇というのは△△という意味でよろしいでしょうか?」
といった具体的な質問をすることで認識の齟齬を防ぎ、後々の「前にも言ったよね」という指摘を回避することができます。
曖昧な理解のまま業務を進めてしまうと結果的に上司の意図と異なるアウトプットになり指摘を受ける可能性が高まります。
質問することは決して恥ずかしいことではなくより正確に業務を進めるための重要なプロセスであることを理解しましょう。
定期的な進捗報告で認識の共有を図る
業務の進捗状況を定期的に上司に報告することも「前にも言ったよね」という指摘を防ぐ上で有効な手段です。
「〇〇の件につきまして、現在△△まで完了しております。今後の予定としては□□に進める予定ですが、何かご不明な点やご指示はございますでしょうか?」といった具体的な報告を行うことで上司は業務の進捗状況を把握し、認識のずれが生じるのを防ぐことができます。
もし、上司が過去の指示と異なる認識を示した場合でも、「〇月〇日の打ち合わせでは、このように認識しておりましたが、改めてご指示いただけますでしょうか?」と以前の認識を伝えることができます。
定期的な報告は上司とのコミュニケーションを円滑にし信頼関係を築く上でも重要です。
「前にも言ったよね」がエスカレートする場合…これはハラスメント?
「前にも言ったよね」という上司の言動がエスカレートする場合それは単なるコミュニケーションの問題を超え、パワーハラスメント(パワハラ)に該当する可能性があります。
パワハラとは職場における優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されるものを指します。
「前にも言ったよね」という言葉自体が直ちにパワハラと断定されるわけではありませんが以下のような状況下で繰り返される場合はパワハラに該当する可能性が高まります。
パワハラに該当する可能性が高いケース
- 頻度と継続性: 一度や二度ではなく、頻繁に、執拗に繰り返される場合。
- 事実と異なる指摘: 実際には言っていないことを「言った」と嘘をついて指摘する場合。
- 高圧的な態度や人格否定: 威圧的な口調や態度で言われたり、能力不足を指摘するような人格否定的な言葉を伴う場合。
- 公開の場での指摘: 他の社員がいる前で一方的に、または見せしめのように指摘する場合。
- 質問や反論の封じ込め: 部下が確認や質問をしようとした際に、頭ごなしに「前にも言ったよね」と拒否する場合。
- 責任転嫁: 業務のミスや問題に対して、実際には指示不足や曖昧な指示があったにも関わらず、「前にも言った」として部下に責任を一方的に押し付ける場合。
- 精神的な攻撃: これらの言動によって、部下が強い精神的苦痛を感じ、職場への意欲低下や不安、恐怖を感じるなど、就業環境が害されている場合。
「前にも言ったよね」という言葉がエスカレートすると、部下は以下のような精神状態に陥りやすくなります。
- 自己否定感の増幅: 自分の記憶力や理解力に自信を失い、自己肯定感が低下する。
- 孤立感と不安: 周囲に相談しても理解してもらえないのではないかという不安や、職場で孤立するのではないかという恐れを感じる。
- 萎縮と行動抑制: 上司に反論することや質問することへの恐怖心が強まり、指示待ち人間になる、ミスを隠蔽するなどの不適切な行動につながる可能性がある。
- 精神的な健康被害: 強いストレスにより、不眠、食欲不振、抑うつ状態など、心身の健康を害するリスクが高まる。
「前にも言ったよね」という言葉が繰り返され、精神的な苦痛を感じている場合は一人で悩まず、周囲に相談することが大切です。
それはハラスメントである可能性があり、放置すれば状況が悪化する恐れがあります。
もう限界…「前にも言ったよね」上司との決別
「前にも言ったよね」という上司との関係に限界を感じ、決別、つまり転職を考えるのは決して逃げではありません。
あなたの心身の健康と、より良いキャリアを築くための正当な選択肢の一つです。
ここでは、転職を視野に入れるべき判断基準と、具体的なステップについて解説します。
精神的な負担が限界を超えている
上司の言動によって、常に強いストレスを感じ、不眠、食欲不振、気分の落ち込みなど、心身に具体的な不調が現れている場合。
仕事に行くこと自体が苦痛で、日常生活にも支障が出ている場合は、これ以上我慢する必要はありません。
ハラスメント行為がエスカレートしている
単なる「言った言わない」のレベルを超え、高圧的な態度、人格否定、公開の場での叱責、責任転嫁などが頻繁に行われ、精神的な攻撃を受けていると感じる場合。
これは明白なハラスメントであり、放置すれば状況は悪化する可能性が高いです。
上司との関係改善が見込めない
れまで様々なコミュニケーションを試みても上司の言動が改善されずむしろ悪化している場合。
第三者に相談しても具体的な解決策が見つからない場合も同様です。
会社に相談しても状況が変わらない
人事部や相談窓口に状況を訴えても適切な対応が取られず上司の言動が改善されない場合。
会社全体としてハラスメントに対する意識が低い、または見て見ぬふりをしている可能性があります。
自己成長の機会が失われている
上司との不健全なコミュニケーションにエネルギーを費やし本来の業務に集中できずスキルアップやキャリア形成の機会が著しく損なわれていると感じる場合。
これらの状況に複数当てはまる場合は、あなたの心身を守り、将来のキャリアを考える上で、転職は有効な選択肢となります。
長く働き続けるなら上司との相性は大事
「仕事内容には満足しているけれど、どうも上司とのコミュニケーションがうまくいかない…」
もしあなたがそう感じているなら、長く働き続けることを考えた時、その現状は決して見過ごせないサインかもしれません。
日々の業務において、上司との関係性はあなたのモチベーション、成長、そして何よりも心の健康に大きく影響します。
どんなにやりがいのある仕事でも、理解のない上司、一方的な指示ばかりする上司、あるいは今回のように「前にも言ったよね」と事実と異なる指摘をしてくるような上司の下では、あなたの能力は十分に発揮されず、ストレスばかりが蓄積してしまうでしょう。
想像してみてください。
毎日顔を合わせる上司との間に、信頼感や尊敬の念がないとしたら…。
あなたの意見は聞き入れてもらえず、些細なことで責められ、本来の業務以外のことで精神的なエネルギーを消耗してしまうかもしれません。
それは、まるで足かせをつけられたまま走るようなもの。
あなたのキャリアの可能性を大きく狭めてしまうだけでなく、心身の健康を害してしまう可能性すらあります。
長く充実したキャリアを築くためには仕事内容と同じくらい、いや、もしかしたらそれ以上に「誰と働くか」が重要です。
上司との良好な関係は、あなたの成長を後押しし、成果を認め、安心して仕事に取り組める環境を与えてくれます。
もし今、上司との相性に不安を感じているならそれはあなたの潜在的な能力が、今の環境では十分に開花しないかもしれないという警鐘なのです。
では、どうすれば自分にとって本当に相性の良い上司、そして長く働き続けられる環境を見つけられるのでしょうか。
そこでおすすめしたいのがミイダスという転職サイトです。
ミイダスの大きな特徴の一つに、あなたのコンピテンシー(行動特性)を科学的に分析する独自の診断ツールがあります。
このコンピテンシー診断を受けることで、あなたがどのようなタイプの上司と相性が良いのか、どのような職場環境で力を発揮しやすいのかを客観的に知ることができます。
自分の強みや特性、そしてそれを活かせる環境を知ることは、転職活動において非常に有利に働きます。
ミイダスのコンピテンシー診断を活用すれば「なんとなく良さそう」という曖昧な判断ではなくデータに基づいた、より納得のいく企業選びが可能になるでしょう。
もしあなたが今上司との関係に悩んでいて長く働き続けることに不安を感じているなら一度ミイダスのコンピテンシー診断を受けてみませんか。
あなたの隠れた才能や、本当に合う環境が見つかるかもしれません。
「もう限界…」と感じる前に、積極的に行動を起こすことが、後悔のないキャリアを築くための第一歩です。
ミイダスは、あなたの新たな可能性を拓くための心強い味方となるはずです。
まとめ
「前にも言ったよね」という言葉に苦しみ、限界を感じているなら、どうか一人で抱え込まないでください。
あなたの状況は、決してあなたのせいではありません。転職は、新たなスタートを切るための前向きな行動です。
勇気を出して一歩踏み出すことで、より良い環境と未来が拓ける可能性があります。
焦らず、自分のペースで、納得のいく決断をしてください。
そして、必要であれば、信頼できる友人や家族、キャリアアドバイザーなどに相談することも検討しましょう。
あなたの新しいキャリアを心から応援しています。
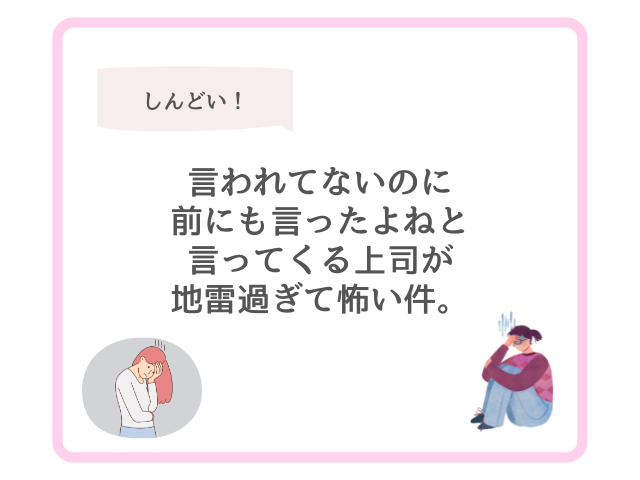
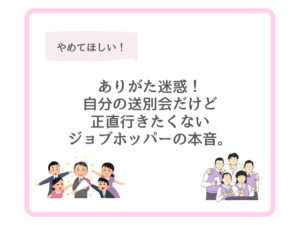
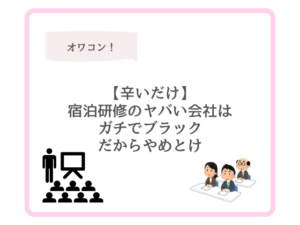
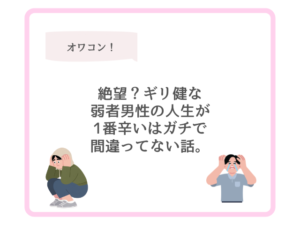
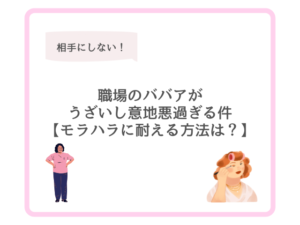
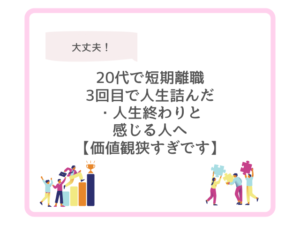
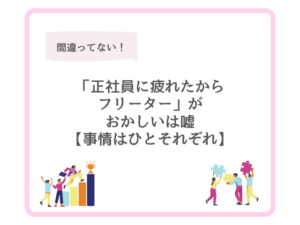

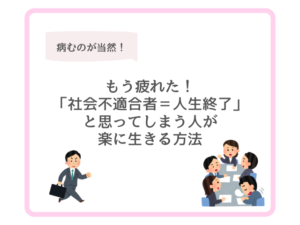
コメント